公開日:
更新日:
14 min read
技術革新異文化の壁を越えて:90年代の分散開発に学ぶAI開発の成功術
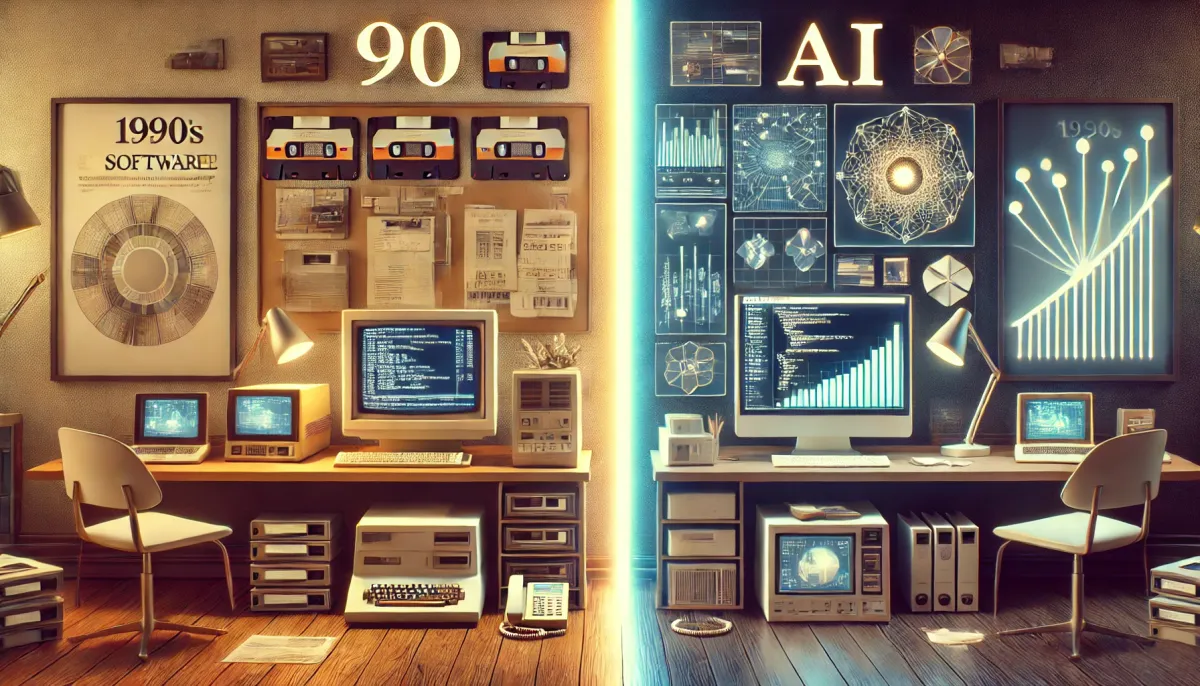
1990年代後半、日本のIT業界は深刻なエンジニア不足に直面していました。 二千年問題への対応が迫る中、状況は一層深刻でした。 当時、私はITベンチャー企業を経営していましたが、エンジニアを募集しても、一般の書籍広告では冷やかしの電話すら来ないほど。 就職情報誌の担当者が絶句したことを今でも覚えています。
大手人材紹介会社からは、こんな言葉を投げつけられました。
「こっちはね、今週中にキャノンに100名、IBMに200名を紹介しないといけないのに、まだ半分も確保できていないんです。 だからおたくみたいな中小企業の相手はしてられないんですよ!」
今ならこんな発言、録音してSNSで晒してやるところですが(笑)、当時はそれも叶わず。 そんな状況の中、私たちは海外に目を向けることにしました。
異文化コミュニケーションの壁
resume.comというサイトで出会った海外エンジニアとの最初の仕事は、今でも鮮明に覚えています。 当時の私は、社内で日本人エンジニアに指示を出すのと同じような感覚で、簡単な英文のメールを送りました。 時差が7時間、しかも相手は夜型でした。 そのため、仕事終わりにメールしておけば、翌朝には返信が来きます。 時差を利用した効率的なスタイルだと考えたのです。
翌日届いた彼からの返信は、予想外のものでした。 いくつかの質問と、私の拙い英語の添削が記されていたのです。 確かにその添削は勉強になりました。 しかし、その後1週間、質問と回答のやり取りが続くばかりで、実際のプログラムは1行も書かれていません。
そこで私は、仕様を事細かに詳しく記述しました。 考えられる質問をすべて想定し、先回りして説明を加えました。 下手くそなりに、可能な限り丁寧な英語を心がけました。 時間もかかりました。
文章量は10倍以上になりました。
転機となった気づき
翌日、彼から返ってきたメールは驚くほど短いものでした。
そして数日後、私の期待通りに動作するプログラムが届いたのです。
この経験から私は重要な教訓を得ました。
文化も言語も異なる相手と仕事をする時、「これくらい分かるだろう」という前提が通用しないのです。 いわゆる「暗黙知」や「常識」は、国や言語が異なれば通じないのです。 皮肉なことに、私自身が開発していたのは翻訳ツールでした。 スクリーン上のあらゆる文字をホバーするだけで、読み取って辞書を引いたり文章を翻訳する世界初のツールを作っていたのです。
コミュニケーションスタイルの変化
この経験から、私はコミュニケーションの方法を大きく変えました。 それまで数分で書いていたメールに、1時間以上かけるようにしたのです。 「これくらい書かなくても分かるだろう」という考えを捨て、丁寧に細かいことまで説明するように心がけました。 効果は劇的でした。
日本のIT業界が抱える構造的な課題
ここで日本のIT業界の特殊な状況について触れておく必要があります。 日本では伝統的に、「プログラミング」という作業自体の評価が低く、単価も安い傾向にあります。 職人を下に、管理職を上に見る文化が強く、その結果、「管理職SE」が増え続け、実際にコードを書くプログラマは海外に依存する構造が定着してしまいました。 1990年代から始まったオフショア開発は、実は人材確保よりもコスト削減が主目的でした。 これは日本特有の「作る人より管理する人を重視する」文化から生まれた歪みと言えるでしょう。
日本独特の「管理職SE」という存在
日本の管理職SEは、世界的に見ても特異な存在です。 本来、SEは高度な技術力を持つスペシャリストであるべきですが、日本では「管理」という役割が強調されすぎる傾向にあります。
具体的には以下のような特徴があります:
-
役割の曖昧さ:技術者でありながら管理職として扱われ、どちらの立場でもない中途半端な状況に置かれがちです。 海外では一般的な「テックリード」のように技術的な指導力を発揮する機会も限られています。
-
実装からの乖離:管理職になると実装から遠ざかることが「昇進」と見なされ、結果として技術力の低下を招いています。 海外では上級エンジニアでもコードレビューや実装に関わり続けるのが一般的です。
-
評価基準の歪み:プロジェクトの成否よりも、予算管理や納期遵守といった管理業務の遂行能力が重視される傾向があります。 技術的な革新や改善よりも、既存システムの安定運用が評価されます。
国際競争力の低下要因
このような状況は、以下のような形で日本のIT産業の国際競争力低下につながっています:
技術面での遅れ
- 管理職SEが新技術への投資を決断できない(技術的な理解が不足している)
- 現場のエンジニアの提案が経営層に正しく伝わらない(技術と経営の橋渡しができていない)
- 保守的な判断により、新技術の導入が遅れがちになる
人材育成の問題
- 若手エンジニアの目標が「管理職」になってしまい、技術力向上への意欲が削がれる
- 実装経験の豊富な上級エンジニアが不足し、技術的な指導が行き届かない
- 海外では一般的な「シニアエンジニア」というキャリアパスが確立されていない
グローバル展開での障壁
- 技術的な議論ができない管理職SEが海外プロジェクトで苦労する
- 海外エンジニアとの協業時に、技術的な判断を任せられない
- プロジェクトの見積もりや技術選定で、国際標準から外れた判断をしがち
自己研鑽の現状
経済産業省の調査から、日本のSEの自己研鑽に関する以下の特徴が明らかになっています。 実際、私も開発現場で、ベテランSEでさえも実装知識があまりにもないことに驚愕しました。
学習意欲の低さ
- 「業務で必要かどうかにかかわらず、自主的に勉強している」と回答したSEの割合は19.0%で、調査対象国中最低[9]
- 「業務外ではほとんど勉強しない」と回答したSEの割合が33.6%と高い[9]
学習機会の活用度
- Web講座による学習(e-learning/MOOC等)の利用率は12.8%と最低水準[9]
- 社外の研修・セミナーへの参加率も19.0%と低い[9]
- 社外コミュニティへの参加率はわずか5.8%[9]
この状況は、日本のSEの競争力低下を表していると言えます。 では、なぜ日本ではSEの自己研鑽意欲がこんなにも低いのか? それは一言では説明がつかない複雑な問題ですが、企業や日本という国が、人を使い捨ててきた歴史が一因であると、私は思っています。
国際競争力の観点から
日本と海外では、SEやプログラマーの位置づけが大きく異なります。
-
海外の評価基準:スキルと実績に基づく評価が一般的で、職種による上下関係は重視されません。 エンジニアは企業経営により近い存在として扱われます。
-
日本の評価体系:システムエンジニアはプログラマーの上位職として位置づけられ、年功序列制により経験年数がポストや給与に影響を与える構造が定着しています。
このような構造的な問題は、日本のIT産業の国際競争力低下にも大きく影響しています。
AIの普及と異文化コミュニケーション
話を異文化コミュニケーションに戻しましょう。
振り返ってみると、この時期の経験は、異なる文化や考え方を持つ相手と、 どのように協働するかという普遍的な課題に対する貴重な学びとなりました。
- 詳細な仕様書を用意することの重要性
- 暗黙の了解を避け、明文化する文化的アプローチ
- 技術者と管理者の役割を明確にすることの意義
しかし、実装を軽んじる日本において、私の経験は価値あるものではないでしょう。 異文化とのコミュニケーションはブリッジSEの仕事です。管理者SEには無縁のものです。
ところが、今、この経験は思いがけない形で新しい価値を生み出そうとしています。
次回は、この経験がどのように現代のAI開発に活かされているのか、 具体的な事例を交えてお話ししたいと思います。