公開日:
更新日:
9 min read
技術革新レガシーシステムの闇:保守開発者の独白
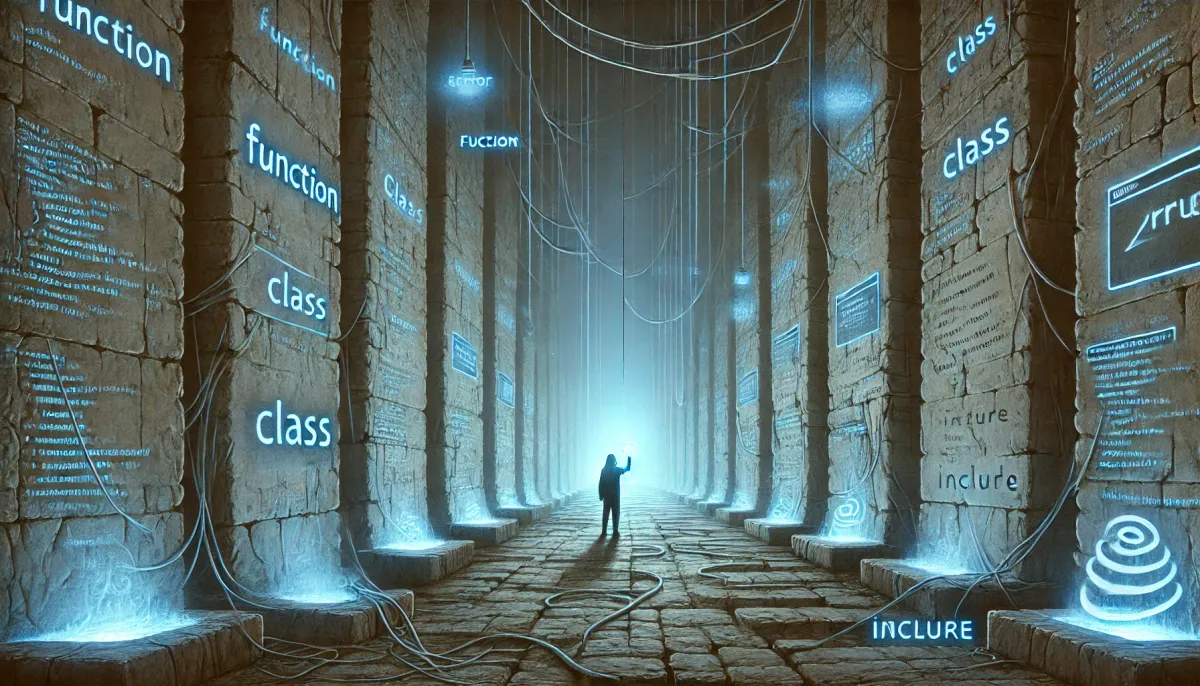
私は今、誰かが作った古いWebシステムの保守を担当している。システムは動いている。 ユーザーは使っている。 しかし、このコードベースは私の心を蝕んでいく。 まるで誰かが書いた暗号を解読しているような、そんな日々が続いている。
システムの概要
簡単な業務システムだ。 DBからリストを読み込み、表示し、編集する。 そんなありふれた機能を持つシステムの保守を任されている。
ここで、Webアプリケーションの歴史を振り返ってみよう。
1. Ajax以前の時代
フォームの送信とページの再読み込みが基本。 シンプルだが、ユーザー体験は良くない。しかし、当時は許容されていた。
2. Ajaxの登場
ページの部分更新が可能に。より良いユーザー体験の実現。フロントエンドの重要性が増加。
3. モダンフレームワークの時代
Reactに代表される宣言的UI。状態管理の整備。フロントエンド/バックエンドの明確な分離。
4.フルスタックフレームワークの時代
Next.js、Astro、Nuxt.jsなどに代表される統合的なアプローチ。 サーバーサイドレンダリング(SSR)とクライアントサイドの機能を統合。 開発効率とパフォーマンスの両立を実現。
問題の本質
このシステムは、Ajaxという新技術を「知っている」が「理解していない」開発者によって作られたように見える。 削除機能だけがAjaxで実装され、他は全て従来の同期通信という中途半端な状態だ。
さらに深刻な問題がある。
- 設計書の不在、命名規則の不統一
- CSSがぐちゃぐちゃ
- JavaScriptにphpを埋め込んである
- どうしてこのようなコードを書いたのが、さっぱり理解できない箇所がある
- 多数のコピペが存在し、同じ処理が複数箇所に散らばっている
- ループを回さずに配列の要素を取得するなど、基本的なプログラミングの知識が欠如している箇所が多数ある
- コードを読んでいるとめまいがする
これらの問題は、現代のWeb開発の基本原則を全て無視している。
- 関心の分離
- コードの再利用性
- メンテナンス性
- デバッグ容易性
まさに、「動けば良い」という考えが生み出した負の遺産だ。これらのコードを見ていると、まるで古代遺跡の発掘現場にいるような気分になる。しかし、考古学的な興味を持っている場合ではない。これらは現役で動いているシステムなのだ。
システム保守者として、我々は日々この混沌と戦っている。新しい機能を追加するたびに、この泥沼に足を取られる。それでも、少しずつでも改善を続けていくしかない。
「車輪を再発明するな」というプログラミングの格言があるが、このシステムは「車輪を歪な形で発明した」典型例と言えるだろう。
そして、最もむかつく頭が痛いのが多言語対応の実装だ。日本語と英語に対応しているが、英語で使用される場面は皆無。それでも全ての文字列がDBに格納され、alt2、alt3といった意味不明なキーで管理されている。これは「柔軟性」という幻想が生み出した負債だ。
虚無との戦い
私は新しい機能を追加する際、あえて文字列をハードコーディングしている。これは「負債」への一つの回答だ。完璧な解決策ではないが、少なくとも新しいコードは理解可能なものにしたい。
しかし、この努力は砂浜に描いた絵のように、潮風に消されていくような虚しさを感じる。システムは動き続け、古いコードは残り続ける。私たちはこの遺産と共に生きていかねばならない。
教訓 - エンジニアリングの重要性
この経験から学べることは多い。特に重要なのは、プログラミングとエンジニアリングの違いだ。
独学でプログラミングをマスターした開発者によく見られる傾向がある。 彼らは確かにコードを書くことはできる。 プログラミング言語の文法を理解し、アルゴリズムを実装することもできる。 しかし、そこには致命的な欠落がある。それは「エンジニアリング」の視点だ。
エンジニアリングとは、単にプログラムを書くことではない。 それは以下のような考慮を必要とする:
- コードの再利用性
- 保守性
- 他の開発者による可読性
- システム全体の設計
- 長期的な拡張性
- チームでの開発を前提とした設計
独学者は往々にして、動くコードを書くことだけに焦点を当ててしまう。 それは車のエンジンを作ることはできても、それを量産可能な形で設計することができないようなものだ。
技術を知っているだけでは不十分なのだ。 システム設計の重要性、実際のビジネス要件に基づく実装の必要性、 保守性を考慮した意思決定の重要性。 これらは全て、プログラミングの能力とは別の、エンジニアリングとしての技術なのである。
このシステムは、まさにその警告として私たちの前に立ちはだかっている。
あなたのコードは、いつか誰かが保守することになる。 その時、その誰かの心を踏みにじることのないように。
私は今日も、このレガシーシステムの迷宮の中で、小さな改善を積み重ねていく。 それは永遠に続く戦いかもしれないが、それが私たちシステム保守者の宿命なのだろう。
他山の石
過去のコードや設計ミスは「負の遺産」だが、それを学びに変えることができれば「他山の石」になる。 独学でプログラミングを身につけた人が増え、情熱を持って現場に挑んでいるが、 プログラミングとエンジニアリングは別物だ。
エンジニアリングとは、未来の自分や他人にとって意味のあるコードを書くことだ。 ただ動くコードではなく、メンテナンスしやすく、改善しやすいコードを目指すべきだ。 それがチームの信頼を築き、より良い成果を生む。
この記事が、コードに対する見方を変えるきっかけになれば幸いだ。 エンジニアとして成長するには、他人の失敗を学びに変え、 自分の価値を高めることが欠かせない。
プログラミング歴40年以上の私も、同じ道を通ってきたのだから。